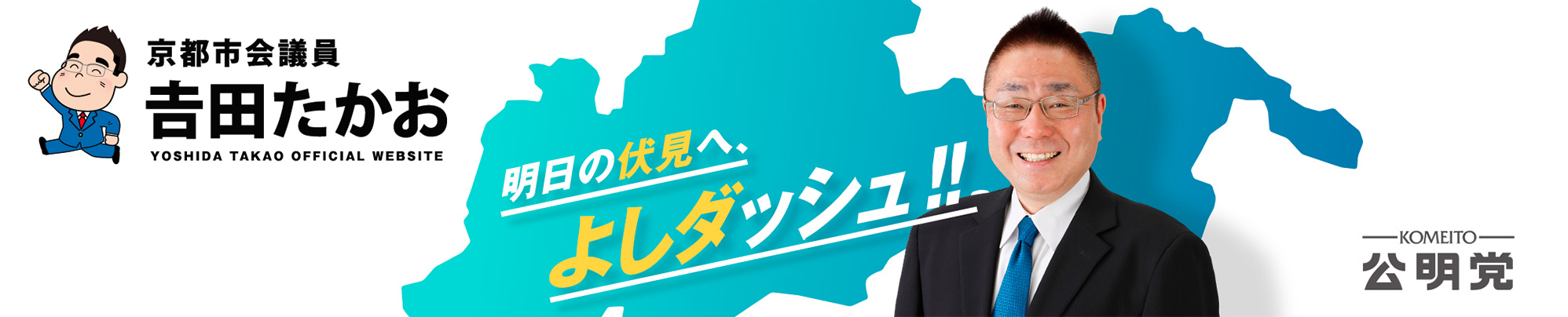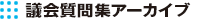自転車条例直後の本会議代表質問
※9月市会に公明党議員団が単独提案した「自転車安心安全条例」が常任委員会で審議され、他会派からの質問に公明党議員が答弁するという、画期的な質疑が展開されました。賛成多数で可決成立し11月17日(偶然にも公明党結党記念日です!)に施行された直後の11月市会では、私吉田たかおが2人分の枠を1人で担当させてもらい、6つの政策課題を取り上げました。「空き家対策」や「高齢者移動支援」など、その後の注目政策を初めて取り上げた意義深い代表質問です。

【自転車安心安全条例の推進】
上京区選出(当時)の吉田孝雄でございます。公明党京都市会議員団を代表し、市政一般について質問させていただきます。市長並びに関係理事者におかれましては、誠意あるご答弁をお願い申し上げます。
時代は、幕末や終戦直後に匹敵する激動期、乱世と言われています。官僚主導や政治主導あるいはコンクリートから人へなど、ワンフレーズポリティックスが騒がれましたが、今や中途半端に頓挫し、身動きが取れないような現状であります。
私は、硬直した中央集権から市民本位の地方分権へと、大きく時代の舵を切るべきであると考えています。地方分権、地域主権のうねりを起こすには、前例主義に固執しない柔軟な発想と大胆な行動力が不可欠です。多くの市民は、二元代表制の一方の旗頭たるべき地方議会の在り方と議員の活動に対して、厳しい視線を注いでおられるのではないでしょうか。
であるがゆえに私は、今こそ議員自らが時代に先んじて研さんを重ねて力を付け、市民のために目に見える形で力を発揮していかなければならないと痛感し、会派の先輩議員と力を合わせ、時間をひねり出して議会改革をテーマに議論を重ねて参りました。
様々な先進事例を研究する中、一問一答や議員間討議といった議会審議の在り方、また超党派の公開議会報告会や傍聴制限緩和といった議会透明化の推進、予算と決算を通年で審議する常任委員会制の導入などなど、時代を先取りする具体的取組について積極的に意見を重ねました。そしてその第一歩として、市民の声を反映した政策を自らの手で一から作り上げようと議員提案政策条例に取り組んだのでございます。
10月に、一部修正のうえ御議決いただいた「京都市自転車安心安全条例」は、このような経緯で約1年掛かりで、手探りで試行錯誤を繰り返しながら少しずつ形になり、ようやく提出できたものです。この場をお借りし、真摯な議論を重ねていただいた各会派の議員の皆さんをはじめ関係理事者の皆さん、調査研究に協力いただいた関係業者や市民の皆さんに心より御礼を申し上げます。
この条例を上程するに当たり、議会直前のタイミングで門川市長に議案の説明をさせていただいたところ、後日市長はご自身のブログで「本市が掲げる自転車施策の取組はもとより、環境施策や歩くまち京都の推進、安心安全の取組等と軌を一にする取組で大変ありがたいこと、また地域主権改革が進む中で、地方議会の強化にも資するお取組です」と記してくださいました。もとより過分な評価とは存じましたが、心温かい励ましを頂だいしたと受け止めさせていただいたのでございます。
条例が成立し今月17日に公布された今、条例に定められた各施策を施行されるに当たり特に注目されているのが、新聞でもクローズアップされた交通安全教育の義務化と、我が会派で実施したアンケートでも多くの要望が寄せられた道路環境整備の2つです。
自転車レーンをはじめとする道路環境の整備は、広報啓発等のソフト事業と比べて予算規模が大きく、危機的財政にある本市では大掛かりな執行は厳しいことは理解できます。しかしながら、昨年度の調査を受け本年度に本格的な社会実験を実施しておられますし、5月議会代表質問における我が会派の湯浅光彦議員からの質問に対しても、由木副市長から関係機関との協議を進めるとの御答弁がありましたので、今後の具体的な予算編成に大いに期待をしているところでございます。
そこでお聞きします。京都市自転車安心安全条例成立に対する市長の評価と、執行に当たって具体的な施策、とりわけ交通安全教育と道路環境整備、特に自転車レーンについて率直なご決意をお聞かせくださいますようお願い申し上げます。
【児童虐待対策】
次に、「児童虐待」についてお聞き致します。痛ましい事件が後を絶たない児童虐待の問題は大変に切実であり、だれもが充実した対策を求めています。京都市の実態をお聞きしますと、平成21年度の通告件数は878件で、504件であった17年度の1.74倍。虐待と認定された件数は、21年度611件で、17年度365件の1.67倍に上り、増加率は全国平均1.28倍を上回っています。
611件中、虐待がひどいので一時保護したケースは44件あり、そのうち19件は帰宅できましたが、25件が保護施設への入所が余儀なくされています。現在24時間の受入体制が取られ、休日や夜間の出動は1箇月平均4回。これが、本市の児童虐待の目に見える範囲での実態であります。
児童虐待問題の第一人者である森田ゆり氏は、虐待を受けている子どもちの小さな叫びをいち早くキャッチして、取り返しのつかなくなる前に被害を最小限に食い止める制度や方法においては、残念ながら余り大きな変化が起きているとは言えないと指摘しています。
私は「コスモス懇談会」と銘打ち、子育て世代のお母さん方と膝詰めで生の声をお聞きしたほか、児童福祉センター院長や児童相談所長はじめ、関係者と意見交換を重ねてきました。その中で実感したことは、しつけと称して暴力を正当化することは許されないという常識を社会に浸透させなければならないということです。
長年残る体罰を容認する風潮も、断じて変えていかなければならないと強く思います。同時に、親の孤独感、閉塞感が虐待の大きな理由であるので、地域の同世代、多世代のコミュニケーションを充実させ、子育て世代への支援体制を創意工夫し地域ぐるみの子育ての仕組みを模索する必要があります。
このような問題意識で、本年5月議会で我が会派の津田早苗議員が関係機関や地域住民との連携とスピード感ある取組の重要性を訴えたところ、市長から「京都の地域力を生かして子供と家庭をしっかりと見守るネットワークを強化し、よりきめ細かな家庭支援を実現する」との答弁があり、一層の充実を期待しています。そのうえで、本日はそれに加えた3点を問題提起させていただきたく存じます。
1点目は、児童相談所の役割を強化する点です。全国児童相談研究会代表委員で子どもの虹情報研修センター研究部長の川崎二三彦氏は、岩波新書「児童虐待現場からの提言」の中で、現在の児童相談所は児童虐待に適切に対応するのに見合った組織体制、十分な人員配置、ふさわしい専門資格、不可欠な研修システム、信頼できるサポート体制、根本的な法律上の枠組み等々の何もかもが整備されないまま、最も困難な業務を担わされ続けていると述べておられます。
本市の児童相談所職員の配置は、一般事務職30名、心理職5名、保健師6名で政令市の中では人口比率が充実していると言われていますが、伏見区に第二児童福祉センターが整備される今がその時期と捕らえ、質量共に強化していただきたい。同時に、激務をこなす職員のメンタルヘルスもより充実する必要があると考えます。
2点目は、教育の重要性です。過激な性情報が氾濫している影響で、いわゆる望まざる出産が問題視されている世相です。虐待問題の根っこに視点を当てるとき、性教育の充実が求められるのではないでしょうか。同時に中学、高校生の時代から、男女問わず親になるための教育も重要です。
生命の尊さや子育ての大切さとすばらしさを学ぶことで、子どもにいらいらをぶつけて暴力を振るうことはあってはならないと心の奥にしみ込ませていくわけです。授業の内容も、保育園や幼稚園とタイアップした実地研修や母親の体験談を聞くなど工夫をしていただきたいと申し上げるものです。
3点目は、国に主導的役割の強化を求めるという点です。子どもへの虐待は重大な人権侵害であり、救えなければ社会にも責任があるのです。虐待の防止は子どもの生命にかかわる重大な国家施策と捕らえ、児童福祉の関係施設の抜本的充実とともに、社会の貧困や矛盾に眼を向けた国民生活支援に思い切ったコストを掛けるべきではないでしょうか。本市としても、現場の立場から国にしっかりと声を届けていただきたい。
以上、提起させていただいた3点、すなわち「児童相談所の役割強化」「教育の重要性」「国への積極的な呼び掛けについて、御所見をお伺い致します。
【うつ病対策】
次に、「うつ病対策」についてお聞きします。平成19年に厚生労働省が行った労働者健康状況調査によりますと、仕事に関して強い不安やストレスを感じている人は6割を超えているそうです。労働者の方だけでなく学生さんや主婦の方も、多くの方が悩みを抱えていらっしゃると思います。
今や、だれもがうつ病になるリスクを抱えていると言っても過言ではありません。「うつ病は心の風邪のようなもので、風邪と同じようにだれもがかかり得る病気だ」という説もございます。手遅れになる前に、風邪と同じくらい日常的に治療が受けられる環境整備が重要であります。
そのためにも、啓発活動の強化と専門家の育成が必要であり、行政の支援も重要ではないかと問題提起させていただきたいと思います。
特に今、認知行動療法が注目されています。これはうつ病に高い効果があると言われているカウンセリング療法であり、薬物療法に匹敵する効果があるとして大きな期待が寄せられています。我々公明党は、国会議員と地方議員がチーム3000を結成し、様々な政策課題に向き合う中、うつ病対策を充実し患者さんの社会復帰を支援する取組を積極的に進めた結果、今年4月から認知行動療法の保険適用が実現しました。
しかし、今の大きな問題は認知行動療法を支える、また行える専門家が少ないということであります。うつ病患者さんのニーズにこたえるには、この新しい治療法の専門家を育成しなければなりません。
ところが、民主党政権が付けた認知行動療法の専門家を育成する予算は何と1,000万円。国としての予算がこの程度では、おざなりと批判されても仕方がありません。イギリスでは、2年前に心理療法アクセス改善プログラムを導入して3年間で約346億円を投入して心理士3,600人の養成を目指しています。菅総理はイギリスからもっとこのことを学ぶべきではないでしょうか。
ようやく本年に、保険の適用がされたとはいえ、現時点では精神科医の診療にとどまっており、普及が進まないのではないかと心配されています。カウンセラーの治療にも保険適用がされるよう現在各方面から真剣な声が上げられています。
精神科医の側からすれば、現在の診療報酬単価が低いため導入したくても困難であるとの声も聞かれます。また心の病について、きめ細かく対策を進めている国の自殺対策緊急強化基金が23年度で打ち切りになってしまうとお聞きしています。
認知行動療法をはじめとするうつ対策への予算の増額と診療報酬単価の改定など、強く国に求める必要があります。それと同時に、京都市立病院でこの治療法を導入して国にその効果を示すことも必要ではないでしょうか。
うつ対策、とりわけ認知行動療法について国に対する要望の強化とともに、本市においても京都市立病院での導入や広報周知の充実など、先進的な取組が重要と考えますが、いかがでしょうか。
【教員事務作業軽減】
次に、「教育問題」とりわけ「教員の負担軽減」についてお聞きします。私自身、中学生と小学生の父親として、PTA活動やおやじの会の活動に参加させていただく中で、学校の先生方の大変さを実感している1人であります。心から敬服し、感謝しています。
ちまたで言われるモンスターペアレンツをはじめ、教員を尊重しないような風潮を何としても変えていかなければならないのではないかと思い、保護者の方々との懇談を重ねると同時に現場の教員の皆さん方とお会いし、意見交換もさせていただきました。
私は、一人一人の子どもの無限の可能性を開き、子どもの幸福を目的とする教育を推進するためには、教員の資質を伸ばし指導力を向上する取組が不可欠であると確信しています。先生を軽んずる生徒や保護者の目を見張らせ、尊敬に変えるような指導力と人間としての魅力にあふれた教員を育成し輩出していただきたい。
そのためにも、教員評価制度が教員にとってネガティブなものにならないよう、現場の声を反映してグレードアップするべきでありますし、効果的な職員研修を充実するとともにメンタルヘルス等のサポート体制をより一層進めていくべきではないでしょうか。
特に、事務作業が多すぎて子どもと向き合う時間が取れないという傾向性が、昔よりも顕著になっているという問題が指摘されています。この問題を解決するための1つとして、私は事務作業を学校以外でもできるような環境整備が重要ではないかと申し上げたい。
教員が遅くまで学校に残らないといけない理由の中に、報告書や計画書、答案や学級だより作成などの事務作業を自宅に持ち帰ることができないという点があります。教員に限らず公務員は、データを何らかの媒体に記憶させて外に出てはならないと決められており、それは情報漏えいを予防する意味で重要であると理解できます。
また本市におきましても、約2年前に個人情報の入ったUSBメモリーを紛失したという事故があったとお聞きしています。情報漏えいの重大性と同時に、このような事故が起こって前途のある教員を処分せざるを得ないことは計り知れない損失ではないでしょうか。
そこで私は、長年ITの企業で仕事をしてきた経験を生かし、1つのアイデアを提案させていただきます。それは「クラウドコンピューティング方式」と言いまして、頑丈な場所にある大型コンピューターにすべての教員のデータを格納し、オンラインで打ち込み、修正等の作業ができるものです。
多くの人々は、個人所有のパソコン本体のファイルフォルダに文書や画像データを保存しています。機械が壊れたり盗まれたら大変ですから、USBメモリー等に保存します。このUSBメモリーは簡単に持ち運べますので、いつでもどこでも作業することが可能になりますが、紛失すると大変なことになるわけです。
そこで、データセンターに置いたサーバに市内の全教員の個人フォルダを設定して文書や画像のファイルを入れておけば、職場でなくても自宅や出張先のパソコンからインターネット機能を駆使してデータを呼び出すことが可能になります。
したがって、パソコンが故障してもデータは失われませんし、持ち運んで紛失する心配もありません。職員室のパソコンで学級だよりなどを作った後サーバに保存させると、自宅に戻って個人のパソコンを起動させネットにつないでデータを呼び出せば、先ほどの続きから打てるわけです。そこで完成させて上書き保存したら、翌日に職員室で呼び出すことができるのです。家に帰ってまで仕事したくないという人は、学校に残って仕事をしても何ら問題ないと思います。
しかし部活の指導などで夕方に事務作業ができない教員は、くたくたになりながら深夜まで残らなければならないケースもあるでしょうし、子育て中の教員が子どもを保育園から自宅に連れ帰った後で再び学校に戻らなければならない日もあるのではないでしょうか。
体調不良で欠勤した場合は、復帰後にたまった仕事が山積みになっていることでしょう。家族の介護で早く帰宅しなければならない教員もいるかもしれません。これからは、勤務スタイルの変化への対応も必要になってきます。その意味で、自宅でもサーバからデータを呼び出して事務作業ができる仕組みは有効ではないでしょうか。
ただし、セキュリティの問題は重要です。メインサーバと各学校の端末との間に絶対に変なウイルスに感染してはなりませんし、ハッカーからもデータを守らなければなりません。これらの対策を強化することと、導入費や維持費などの予算が必要になるという2点の心配は確かにあります。しかしながら、現実に多くの民間企業は、この方式を導入し効果を発揮しているのです。
教員の事務作業軽減を図り勤務スタイルの変化に対応するためにも、クラウドコンピューティング方式を教育現場で導入してはいかがでしょうか。御見解をお聞かせください。
【空き家対策】
次に、「空き家問題」についてお尋ねします。2008年の住宅・土地統計調査によりますと、京都市内全域で11万戸の空き家があるとのことです。人口減少や高齢化が進み、所有者不明のいわゆる管理放棄不動産がこの数年で急激に増加しています。
老朽化した空き家が放置されたままで危険家屋の状態になると、台風などの自然災害時に倒壊の可能性が高まりますし、季節によっては害虫の発生によって近隣住民の生活を脅かしていくとの懸念もあります。また不法投棄が進むとか、犯罪の温床になりかねないとの指摘もあり、正に防犯・防災・衛生・景観という多岐にわたる問題でございます。
私の住む上京区は、市内でも危険家屋が多くたくさんの市民の皆さんから相談が寄せられています。野良猫のすみかになって悪臭や騒音の被害も少なくないとお聞きします。私の近所ではイタチも目撃されており、事態は深刻なのです。
都市計画局の建築安全推進課では、住民からの相談を受けて空き家の所有者を探し出したり、安全対策の指導を行うなど対策を講じています。現在本市において一戸建ての空き家が危険家屋になっている実態は、通報されていないものも多いと思いますが、行政指導を進めているところは113件、そのうち30数件が危険な状態で長年放置されているとのこと。相続登記されないままの物件は相続人がねずみ講のように増えてしまうといいますし、係争中のケースでは相続人が特定できず交渉が困難であったりして進展しないのが現実であります。
特定された場合も、行政からの指導に対し建て替えたいのはやまやまだが、経済的余裕がないなどと理由を付けて何年も放置されており、非常に厳しい状況にあるのです。また空き家を所有する側のご意見として、だれかに貸すにしても信頼できる仲介業者が分からないとか、貸したら返ってこないのではないかという不安があるとのことで、従来の行政指導だけでは限界があるのも事実ではないでしょうか。
市民の生活を守り、安心安全のまちづくりを推進するためにも、空き家が管理不全な危険家屋状態となる前に予防しなければなりません。その対策として、本市では「地域連携型空き家流通促進事業」を今年度から着手し、モデル事業として上京区の春日学区と東山区の六原学区の2箇所で本格的な地元協議が開始されました。
事業の特徴は、地域に根付いたコーディネーターが地元の良さや暮らしのルールを伝えながら空き家の所有者と入居希望者をつなぐというもので、地元学区が地域ぐるみで主体的に取り組む体制を採っておられます。
この事業は、私が以前から申し上げているように、上京区や東山区など少子高齢化が進んでいる地域に、若者や子育て世代が転入してくるような魅力的な、そして持続可能なまちづくりを進めていくための取組としても大いに期待されるのですが、今は始まったばかりで見守る段階です。
この「地域連携型空き家流通促進事業」の成功に向け、実効力を発揮するために地域住民の声を積極的に反映させるとともに、全庁挙げて総力を結集して取り組んでいただきたいと思います。御所見をお聞かせください。
空き家対策については、もう1点申し上げることがございます。上記の事業が進んだとしても、危険家屋となった空き家がすべてなくなることは考えにくい。中にはコーディネーターの呼び掛けに応じないケースもあるのではないでしょうか。
そう懸念される理由の1つに税負担の問題があります。危険家屋化している空き家のままの方が、改築したり更地にするよりも固定資産税が安いとのこと。地方税法では資産価値に応じて課税すると定められており、資産価値は新築や更地よりも老朽家屋の方が低いため結局は手を付けない方が負担が少なくて得であるという理屈になるわけです。
私は、行政指導を無視したり督促に応じないような悪質と言われても仕方がないケースには、警察等と連携して強制的な措置ができないのかどうか他都市の事例を含め調査を重ねました。埼玉県所沢市は、10月1日から「空き家等の適正管理に関する条例」を施行しました。
この条例は、空き家などが管理不全な状態となることを未然に防ぐことにより、市民生活の環境保全及び防犯のまちづくりに寄与することを目的と定め、所有者には空き家の適正な管理を義務付けるとともに、市民へも空き家に関する情報提供を求めています。
また行政は、空き家の実地調査を行って所有者に指導・勧告を行い、これに応じなければ必要な措置を講ずるよう命令、それでも改善されなければ所有者の名前や連絡先などを公表し、最終的には警察などの関係機関と協議し、撤去を依頼することもできるという思い切った内容です。
条例を受けて所沢市民の方々は、「空き家のブロック塀が倒れても、所有者に連絡したがつながらず困っていた」あるいは「空き家への放火が怖く眠れない日もあった」「条例の施行で早く空き家を改善してもらいたい」などと語っておられるとのことです。
地元の公明党議員に取材したところ、施行されたばかりで具体的な件数は把握していないが、市当局が所有者に連絡を入れた際の反応が条例制定前とは全然違うということでした。また和歌山県でも、空き家対策の条例制定に向けた審議会が立ち上がっているとお聞きしています。
本市においても、放置された空き家等が管理不全な危険家屋の状態となることを防止し、安心安全のまちづくりを推進するため、部局の壁を越えた取組を進めるとともに「空き家対策条例」を制定すべきと考えます。市長のご所見をお伺い致します。
【高齢者移動支援】
最後に、「高齢者福祉」に関してお聞きします。今、買い物弱者あるいは買物難民、また医療難民という言葉をよく聞きます。近い将来、買い物にさえ不自由する高齢者の方が増えるのでないか、そのような方々への対策を今から取り組まなければならないのではないかという問題意識を持っています。
経済産業省の今年5月の報告書によりますと、買い物弱者と呼ばれる高齢者は全国で600万人と推測されています。私の住む上京区をはじめとする旧市街に限らず、市内の各行政区においても高齢化が進む中で地域密着の商店街の必要性が高まっていますが、大型店の進出等でシャッター商店街が増えているという深刻な実態がございます。
同時に、その商店街に行くことさえもできないくらい足腰が弱っておられる高齢者の方も増えているというのが現状ではないでしょうか。現在61箇所の地域包括支援センターを拠点に、在宅介護支援センター、福祉事務所ほかの諸機関、社会福祉協議会や民生児童委員さん、老人福祉員の皆さんが役割分担されて、地域に根差した介護や生活面のサービスについてきめ細かく対応しておられますが、2025年問題と言われ後15年たちますと要介護認定を受ける方が今の倍に増えるという試算もあり、今の段階から着実に対策を講じていくべきであります。
9月議会の本会議代表質問で、我が会派の久保勝信議員の質問に答え、市長からネットスーパー構想が発表されました。高齢者の自宅にインターネットの端末を設置し,必要な商品を注文したら配達されてくるというシステムです。
これは、地域ぐるみのデリバリー制度をより実用的に進めるという点で期待されるものと考えますが、高齢者が使いこなせるのかどうかという懸念や、ますます家から外に出ない生活が続いて不健康になり足腰の衰えが促進されてしまうとの心配も出て参ります。
そこで、これを一歩進めた仕組みを提起させていただきたいと存じます。それは、デリバリーではなく家から出て外の空気を吸って、ご近所の方とあいさつを交わし、医療機関や商店街に足を運ぶための新しい交通システムとして、都市型のデマンド交通とタイアップしてはどうかということであります。
デマンド交通は、他府県では山間部などの人口過疎地域で多いのですが、逆に住宅密集地の都市部で導入してはどうかという発想の転換で、上京区で地域ぐるみで準備会が設立され、地元学区連合会の方々や商店街、医療機関と大学が連動して、2年間という時間を掛けて様々な角度で研究されてきました。
昨年12月、モデルとして仁和学区でアンケート調査を実施されたところ、実に1,000名を超える方々から回答が寄せられたということで、地域の方々の関心も高いことが明らかになっています。
また、来月から第2回目の聞き取り調査を実施される計画です。このデマンド交通が定着すれば、自宅まで往診に来てもらうことを待つのではなく、ご近所の友人と乗り合わせて会話に花を咲かせながら医療機関に行けますし、診療が終わった後もすぐに帰宅せずに、商店街に足を伸ばしてお店とコミュニケーションを取りながら買い物を楽しむこともオーケー。買い物難民、医療難民と言われる高齢者福祉課題に資すると同時に、商店街活性化にも可能性が広がると大いに期待しているわけでございます。
また、行政主導ではなく市民の発意で地域ぐるみで着実に進めておられるこの取組は、先のネットスーパー構想が定着するための第一段階として、タイアップすることが可能ではないかと考えます。
つまり、利用者さんがデマンドバスに乗って医療機関まで出掛け、診察を受けるまでの時間に待合室に設置されている端末の機械で商店街の画面を呼び出し、タッチパネルの簡単な操作でお店と商品を指名して予約します。そして診察が終わって、デマンドバスで家に戻った時間を見計らってお店から商品が届くわけです。
端末を医療機関に設置することで操作面に不安な方は、周囲にいるスタッフに助けてもらうこともできますので、自宅にパソコンを設置する方式と比べても高齢者の方は受け入れやすいのではないでしょうか。ネットスーパー構想が、本来の目的である高齢者対策とりわけ買い物難民問題への環境整備を推進するための第一歩として、都市型デマンド交通とのマッチアップは一つのヒントになると申し上げたい。
このネットスーパー構想が実効力あるものになるためにも、上京区で進めている西陣デマンド交通準備会の取組に対して具体的支援を進めていくことが、これからの京都市の多くの地域の先行事例となるのではないかと考えます。市長の御答弁を求めます。以上で私の質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。
〔答弁〕【自転車安心安全条例の施行】(門川市長)
吉田孝雄議員のご質問にお答え致します。まず、「京都市自転車安心安全条例」についてでございます。この条例は、交通事故における自転車事故の割合が年々高くなり、歩行者に対する重大な事故も増加しているなどの状況のもと、自転車の安全利用をより促進していくため議員提案により制定されたものであり、地域主権時代にふさわしい条例であると認識しております。
自転車は、環境に優しく市民にとって気軽に利用できる健康で便利な乗り物であるため、本市ではこれまでから京都府警と連携しつつ、地域の皆様が主体となった自転車マナーの啓発活動や自転車を安全快適に利用できる環境づくりに取り組んできたところであります。
とりわけ、子どのころからの安全教育が重要であると考えており、この条例の柱の一つである交通安全教育につきましては、これまでから学習指導要領等に基づき、本市独自の副読本「安全ノート」も活用しながら各学校で計画的に実施されるとともに、PTAや地域団体等の関係機関との連携のもと、地域ぐるみの交通安全教室が各小中学校で実施されております。
さらに京都府警と連携し、4年生以上を対象に授業と実技指導を組み合わせた自転車教室を実施する学校が増えてきており、これまで7,000人を超える児童が受講し自転車運転免許証の交付を受けております。
今回の条例を契機に、すべての子どもたちが被害者にも加害者にもならないため、更なる交通安全教育の充実を図って参ります。これらの取組を一層効果的に推進するためには、自転車歩行のマナーの向上やルールの周知とともに、自転車と歩行者が共存してお互いに安心安全に通行できる自転車通行環境整備も必要であると考えております。
しかしながら、本市の道路は概して狭あいで交通量も多いことから、吉田議員ご指摘の自転車レーンなど自転車走行空間を車道に求めた場合、荷さばきなどの車による通行阻害に対する安全性の確保やバス等の公共交通に与える影響など整備に向けた課題は多くあります。
そのため、本年11月中旬に御池通の北側歩道において歩行者と自転車を分離する実証実験を実施し、実験の効果・課題について検証を進めているところであり、また現在五条通において国による実験も行われているところであります。
今後、京都府警や国との協議を進め、実験中に実施したアンケートや実態調査の結果を総合的に見極め、環境に優しく本市が掲げる歩くまち京都にも寄与する自転車通行環境の整備について本条例の趣旨を十分踏まえ、しっかりと検討を進めて参ります。
【児童虐待防止】(門川市長)
次に、「児童虐待防止」についてであります。児童虐待は、子どもの心身の成長や人格の形成に大きな影響を与え、かけがえのない命さえ脅かす深刻かつ重大な人権侵害であり、決して許されるものではありません。
このため本市では、児童相談所・子ども支援センター・保健センターをはじめ、学校・幼稚園・保育所・様々な地域団体と連携し、児童虐待の未然防止・早期発見・早期対応に全力を挙げて取り組んで参りました。
吉田議員ご指摘の児童相談所につきましては、これまでから国の基準を大きく上回る児童福祉司を配置するなどの体制強化とともに、児童虐待の通報に対応する24時間の連絡体制の確保などに取り組んで参りました。
更に、現在第二児童福祉センターの平成24年度の開設に向けて取り組んでおり、児童相談機能・体制の一層の充実を図るとともに、組織的な対応による職員の精神的な負担軽減にも十分配慮しながら、迅速かつ的確な支援が実施できるよう努めて参ります。
次に、性教育等の充実についてでありますが、各学校におきまして保健体育科等で性に関する正しい知識の習得に加え、人とのコミュニケーションや命の大切さ等、子どもたちの発達段階に応じた授業が展開されております。
また、家庭科等では乳幼児の発達等について学び、理解を深めるとともに、すべての中学校2年生が体験する生き方探求・チャレンジ体験において、保育所や幼稚園等での就業体験を通して、幼少の者に対する思いやりの心をはぐくみ、自分がどのように家族の愛情を受け支えられてきたかを学ぶことにより、生命の尊厳への理解を深め家族に対する敬愛の思いなどをはぐくむ取組が進められております。
今後、教育委員会において、こうした取組の質的な充実を管理者のご理解・ご協力のもとに進めて参ります。
次に、国への要望についてでありますが、児童虐待は国を挙げて取り組むべき課題であり、児童相談所の体制強化のための財政措置や親権制度の見直し等の法制度の整備に向けて、引き続き国にしっかりと要望して参ります。今後とも、京都の地域力を生かし、市民と行政が一体となって児童虐待を防止し、すべての子どもたちが笑顔で暮らせる社会の構築を目指して、強い信念と決意を持って取り組んで参ります。
【空き家対策】(門川市長)
次に、「空き家対策」についてでございます。市内における空き家の増加への対応は防犯・防災の面だけでなく、良好な地域コミュニティの維持や都市の活性化という面からも、さらに放置された空き家が危険家屋となるという観点からも、喫緊の課題と認識しております。
このため、本年3月に策定致しました「京都市住宅マスタープラン」において、空き家の増加の抑制や適正な維持管理による危険住宅化の防止を施策の方向としてお示しし、シンボルプロジェクトとして地域と連携し、空き家の流通を促進する仕組みづくりを掲げたところであります。
今年度は、都心部の2学区をモデル地区に選定し、地元の自治組織や不動産事業者、市内の大学等が連携して、空き家の情報と併せて地域の魅力や住まい方のルールを発信し、空き家の所有者と入居希望者の双方が安心して空き家を活用できる仕組みづくりを進めております。
このモデル事業が、具体的な空き家活用の成果を上げることを目標に進めており、既に地元の皆様との協働により活用可能な空き家の掘り起こしや所有者への協力要請などを行っております。
また、新たな地域の魅力の発掘や情報発信については、地元の皆様と区役所をはじめとした関係部局、さらに京都市景観・まちづくりセンターが連携して取組を進めているところであります。
今後、この空き家流通の仕組みを同種の課題を抱える地域に広げていくことにより、良好な地域コミュニティと住宅ストックを有効に活用した京都らしい住まい・まちづくりを市内全域で進めて参ります。
一方、吉田議員ご指摘のように、この仕組みによっても流通に乗らず適正な管理が行われないまま放置され、結果として危険家屋となるものもございます。こうした家屋を発生させない予防的な対策につきましても、多角的な視点から検討を進めて参ります。
ご提案の「空き家対策条例」につきましては、他都市の状況も注視しながら研究して参ります。なお、危険家屋につきましては、これまでから建築基準法に基づき指導を行ってきており、指導に従わない者に対しましては行政代執行も視野に入れ、き然とした対応を行っていくべく、そして安心安全の確保に全力で取り組んで参ります。
【高齢者移動支援】(門川市長)
次に、「高齢者の買い物支援」についてでございます。吉田議員ご指摘のとおり、独り暮らしの高齢者の増加や、お住まいの身近な場所での商店の閉鎖などから、都心部においても食料品等の日常的な買い物が困難な状況にある、いわゆる「買い物弱者」と呼ばれる方々の課題が生じてきていると認識致しております。
国におきましては、買い物支援を含む生活支援の在り方について、現在社会保障審議会で議論されており、本市でもその動向を注視しつつ、次期「京都市民長寿すこやかプラン」を策定する中で、ニーズの把握や支援内容等に関する議論を行っていくことと致しております。
こうした状況のもと、本市においては買い物支援策の1つとして、市内にモデル地区を選定し、民間事業者と連携したITの活用により、自宅に居ながら商品の注文や受渡しが可能となるような流通システムの構築と実証実験に取り組むことと致しました。
一方、吉田議員ご指摘の西陣デマンド交通準備会においては、地域が主体となって交通行動に関する住民へのアンケート調査を行われております。この調査は「スローライフ京都大作戦」の一環で実施しているモビリティ・マネジメントの1つとして、地域住民の皆様や大学等と連携し、コミュニケーションを図ることにより、住民の皆様の自主的な交通行動の変化を促すものであることから、京都市も支援しているところであります。
今後は、地域が主体になって努力されているこうした取組の推移を見守りながら、流通システムの構築に当たっては、来年度のできるだけ早い時期に高齢者の買い物困難度等の実態調査を行い、そのニーズを把握するとともに、地元や関係団体のご意見を反映した、より使いやすいものとなるよう取り組んで参ります。私からは以上でございます。
【うつ病対策】(細見副市長)
私からは、「うつ病対策」についてお答え致します。うつ病は、自殺の大きな原因となるなど、社会的に大きな課題となってきておりますが、その対策としては、市民1人1人が病気に対する正しい知識を持ち、家族や周囲の方、相談窓口の職員等がうつ病の兆候に気づき、専門の相談機関や医療機関につなげることなど早期に発見し、適切に対応できる体制を作ることが必要であると考えております。
このため本市では、市民の心の健康づくり及び自殺対策の双方の観点から、市民や相談機関の職員、かかりつけ医等を対象にしたうつ病に関する様々な講演会や研修会の開催、リーフレットの配布、かかりつけ医と精神科医の連携を図る交流会の開催など、様々な取組を進めており、今後更にその取組を強化して参りたいと考えております。
議員ご指摘の認知行動療法につきましては、うつ病に対する精神療法として開発され、科学的に効果があるものとして診療報酬対象の医療に位置付けられたところでございますが、議員ご指摘のとおり、この療法に習熟した医師が少なく、その養成が大きな課題となっております。
また、この療法の実施には、患者1人当たりに掛ける時間が大きく、他の患者の診療時間も確保する必要があることや、診療報酬単価が低いことによる採算性の問題から、京都市立病院に直ちに導入することは難しいと考えておりますが、市立病院として医師等の職員を研修に派遣することと併せ、将来の実施の可能性について検討して参ります。
同時に、国に対しては、認知行動療法の普及に向けて、実施できる医師の育成や診療報酬の適切な設定、また国民への情報提供等について、今後要望して参りたいと考えております。以上でございます。
【教員事務負担軽減】(高桑教育長)
コンピューターを活用しての「教員の事務負担軽減」についてお答え致します。本市では、校内LAN整備、教員1人1台のパソコン配備を行い、併せてこうした環境を生かした学校の事務の効率化を図るため、校長会・教頭会等の代表も参加するプロジェクトを立ち上げ検討を進めて参りました。
その結果、学校経理事務の電算化、イントラネット上の掲示板や電子回答システムを活用した文書事務の大幅な削減、さらに学校のホームページを簡単に作成できるシステム等の導入など、教員の業務の省力化に大きな成果を上げて参りました。
一方、教職員は個人情報をはじめ重要情報を取り扱うことも多く、情報漏えいを予防する観点からも、現在教職員が業務上のデータ等を学校外に持ち出すことは禁止しておりますが、議員ご指摘のとおり、子育てや介護等のやむを得ない事情により、自宅等で事務作業を行う場合の情報管理上の安全な環境整備も必要となってきております。
議員ご提案のクラウドコンピューティング方式につきましては、情報管理上のセキュリティに万全を期すうえでも先進的な技術であり、導入を図っている企業等も多く大変注目を集めております。
本方式の導入のためには、利用する教員すべての認証が必要となりますが、来年1月には全市の学校のパソコンデータを集中管理しているサーバの更新に併せて、より高いセキュリティを確保することが可能となるため、あらかじめ登録されたパソコンから事務作業ができる形式のクラウドコンピューティング方式の導入について検討して参ります。
今後とも、業務の情報化等を推進するとともに、学校運営全般の見直しを図り、教員が子どもと向き合う時間を増やすことができるよう努めて参ります。以上でございます。
(議会改革への熱い思いをこめて質問しました。その後の京都市は「自転車政策」「空き家対策」「教育のIT活用」などで、全国をけん引する成果を挙げ、他の自治体から大きな注目を集めるに至っています)
※平成22年度は教育福祉委員会に所属し、福祉や子育て支援、教育の重要課題について議論を重ねるとともに、審議会やセミナーなどに積極的に参加して研鑽を深めました。民主党政権での野党時代でしたが、現場の生の声を受け止めて「建設型」の質疑を心掛け、次の時代を拓く斬新な視点と柔軟な発想を志して頑張りました。京都市はその後に「心の病」と「ひとり親」を含め、福祉政策が具体的に前進したのが誇りです。> 続きを読む
※膨大な累積赤字が続く交通事業の健全化に向け、粘り強く委員会の場で質疑を積み重ねていく中で、その総決算と言うべき公営企業予算委員会の総括質疑に登壇。市民の生の声を求める場の設定や駅ナカビジネスなど、具体的な政策を提言しました。当時は上京区選出でしたので、左胸に区のイメージキャラクターをあしらったバッヂを着用して臨みました。> 続きを読む
※1期目の3年目は公共交通やインフラを所管する交通水道委員会に志願し、現地調査を重ねて議論を重ねていきました。公営企業決算の総括質疑では「市立病院」の患者家族のクレーム対応や院内保育所の改善を提言。> 続きを読む
※1期目の第3回目の本会議代表質問。爽やか訪問やコスモス懇談会などの意見交換、現地調査を重ねる中で、市民目線の政策提言を志向して本会議で意欲的に質疑を展開しました。子育て世代の方々から寄せられた声が具体的な政策に反映したことなどが注目され、公明党結党記念日の1日後の11月18日(支援組織の創立記念日)の公明新聞1面にコスモス懇談会の模様が掲載されました。> 続きを読む
※平成20年度は1期目の2年目。くらし環境委員会の副委員長として議論を重ねました。決算委員会の総括質疑で、「文化芸術」「Do You KYOTO」「地球温暖化」「循環型社会」について問題提起。市民の声を生かした柔軟な発想・縦割りを克服した施策の融合・現場を歩く中で想像力を創造力に生かす、という吉田たかおのコンセプトの萌芽が見えますので紹介します。> 続きを読む